絵画とは何だろう。
作者の意志が絵画を可能にするのか、見る者の想像力が絵画を成り立たせるのか。
「絵画を見る」とはそこに未体験のなにかを発見することでありたい。
JR天王寺駅西側の壁面にあった。
おそらく単なる汚れだ。
しかし、汚れには見えない。
人間の意図を感じる。
じっくり眺めていたら、半円形の何本もの線が山の連なりのようにも見えてきた。
壮大な山の風景がそこにある。
拭き取ろうとした痕跡がある。
シンプルなアーチを描く汚れ。
他の場所にも「描いては消し、描いては消し」という跡が残っている。
木炭デッサンを思い出す。
無意識と意識は何を描こうとしていたのだろう。
他の場所にもあった。
張り紙があったので近寄ってみる。
----------------------------------------
迷惑です。
スケートボード禁止
この場所では、
スケートボード等の行為が
禁止されています。
発見した場合は、
警察に通報します。
JR西日本 天王寺駅長
----------------------------------------
おそらくこの「汚れ」に言及する張り紙だろう。
しかし、あまりにも絵画的な迷惑。
絵画的
てき 【的】
(接尾)
① 名詞およびそれに準ずる語に付いて,形容動詞の語幹をつくる。
㋐ 主に物や人を表す名詞に付いて,それそのものではないが,それに似た性質をもっていることを表す。…のよう。…ふう。「百科事典―な知識」「母親―な存在」
㋑ 主に抽象的な事柄を表す漢語に付いて,その状態にあることを表す。「印象―な光景」「積極―に行動する」「定期―な検診」
㋒ 物事の分野・方面などを表す漢語に付いて,その観点や側面から見て,という意を表す。上(じよう)。「学問―に間違っている」「事務―な配慮」〔(ア)~(イ)は,もと中国,宋・元の俗語で「の」の意味を表す助辞であったものを,明治以降,英語の -tic を有する形容詞の訳語に用いたことに始まる〕
② 人の名前・行為・職業などを表す語,またはその一部に付いて,それに対する軽蔑や親しみの気持ちを表す。「泥―(=泥棒)」「取―(=ゴク下位ノ相撲取リ)」「正(まさ)―(=正雄・正子ナド)」〔中国の俗語にあったのをまねたもの〕
絵画そのものではないが、それに似た性質を持っている。
絵画に似た性質・・・その「似た性質」というのがとても大事な問題を含んでいるのではないかと思ったりもする。
それは、表現という言葉のまやかしについてである。
2023/04/26
ふたつの偶然.
2023/04/26
70年代美術の後遺症。
2023/04/26
垂直線が乱れると、写真の中に重力を感じる。
2023/04/24
大学に入った頃、古市のタサカ写真館でジャコメッティの写真を複写してもらった。
先日、古い荷物を開封したらこれが出てきた。
「人間とはなにか」という写真集の裏表紙にジャコメッティの顔写真(Franz Hubmann/Austrian, 1914–2007 の写真作品)が載っていて、僕はそれを複写するという暴挙に出たのだった。
顔写真を複写するなんて まるでアイドル扱いだ。
そのジャコメッティからはいろいろ学ぶことがあって、おそらくそこが僕の出発点だと思っている。
訳あって所持品の整理をしているのだけれど、この薄っぺらい紙が棄てられない。
ページがばらばらになりそうなこの写真集もまだ手元にある

フランツ・フブマン(Franz Hubmann)をググっていたらこの写真が出てきた。
複写した僕のジャコメッティはトリミングされたものだった。
当時はググることもできず、この情報までたどり着けなかった。
時代だな・・・。
ジャコメッティの複写写真の背後に写っている直線は、大学3年生の頃の版画作品だ。
正方形のケント紙いっぱいに、斜めの正方形が黒一色で刷ってある。
リトグラフでの作品だが、処分してしまった。
実物がないからここに再現してみる。
色気のない単純な作品だ。
2023/04/24
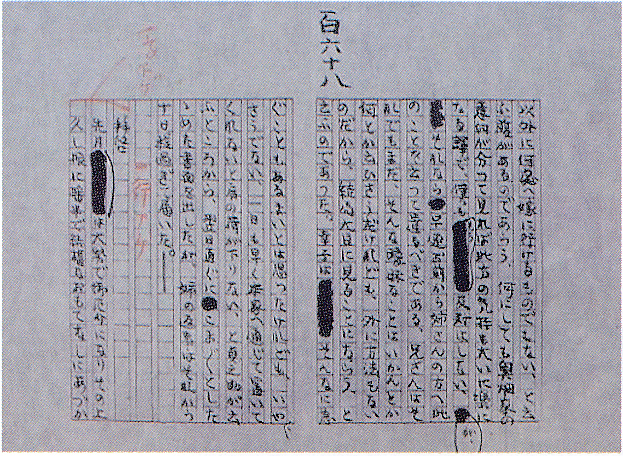
芦屋市 谷崎潤一郎 記念館 に行ってきた。
そこで彼のナマ原稿を見た。
推敲の跡が徹底していて惹かれる。
修正する箇所に二本線を引くようないい加減さではなく、鉛筆で真っ黒に塗りつぶしてある。
学芸員の井上勝博さんによると、修正する前の文章を他人に絶対読まれたくなかったからだそうだ。
筆でも原稿を書くが、その場合の修正も文字が読めなくなるまで執拗に黒く塗りつぶすのだという。
原稿用紙は略字もなく、楷書で一字一字はっきり書いてある。
なんと几帳面なのだろうと感心したら、これは代書だという。
いわゆるペン習字のように整った形ではないが読みやすい文字だ。
原稿の代書、ということに驚いた。
要するに、正確に編集者に伝えるために誰かに頼んで まずは清書してもらうようだ。
それを読み返しながら書き加えたり塗りつぶしたりする。
これが谷崎の原稿の書き方らしい。
したがって彼の肉筆は書き加えた推敲部分から知ることができる。
代書してもらうほどの悪筆かと思ったら、意外にも楷書で丁寧な文字だ。
曖昧な部分を徹底的に排除し、伝達の正確さを大切にする谷崎の姿勢が原稿からうかがえた。
かつて宮沢賢治の原稿を見たことがあるが、それは最初に書いた文章を読むことができるような消し方だった。
だから、賢治がどのような文言を選び文章を組み立てていったのか、思考のプロセスを知ることができてとても面白かった。
しかし、谷崎はこういう他人の興味を完璧に閉ざす。
潔癖というか、秘密主義というか・・・そういう性癖をこの原稿から生々しく感じた。
記念館では今年の12月に「谷崎が・棄てた・「細雪」~反故原稿の中の名作」(仮)という展覧会を計画している。
館は「細雪」のための原稿を書き棄てた反故原稿7枚を所有していて、それの展示をするようだ。
先述したような形式で反故原稿には推敲の跡があるが、現存している「細雪」とは異なる内容が記されているという。
潔癖で秘密主義の小説家が意せず残した手違いのようで興味深い。
2023/04/16
------------------------------------------------------
今日、谷崎潤一郎記念館・館長の砂田円さんから仕事上でのメールいただいた。
砂田さんにこのブログを無理やり読んでいただき、有り難いことにその返事もついでに頂戴した。
それによると、当日展示してあった谷崎の原稿、「東京をおもう」に関しては代書だったとのことで、谷崎の原稿が全て代筆であった訳ではないということだ。
むしろ代筆は非常に珍しいということだ。
私の取材の至らなさで、思い違いをするところだった。
間違いを正していただき助かった。
考えてみたら、原稿を代書してもらうとは面倒なことだ。
常にそんなことをしていたら大変だ。
「東京をおもう」を執筆中には、特に事情があったのに違いない。
そうなると代書のこの原稿は・・・なんとレアなものだろう。
2023/05/05


大阪駅前第二ビルの地下にあった店が閉店していた。
店といっても、通路脇の壁面を利用した商品棚に、生活雑貨とタバコなどを売る店で私が学生の頃は大阪の地下街で都道府県の物産を売る店などが軒並み並ぶ光景もあった。
入り口のない、中に立ち入ることができない商品棚だけの店である。
店員が一人通路に椅子を出し商品を売っている。
どの店も暇そうだった。
そういう様子が記憶の中の「おおさか」風景の一つでもあった。
今日、張り紙がしてあった。
一部分セロテープで貼った修正部分があって「四十七年もの間・・・」と書かれてある。
気になって側面に回って見てみたら、はがれかけた隙間に「四十数年・・・」とあった。
四十数年続けてきた店の歴史を書いてはみたが、正確に年数を表記したくなったのだろう。
自分の歴史をいとおしく思う気持ちがそこに現れているようにも思えた。
それにしても、この緊張感のない張り紙はどうだろう。
閉店前に何度もここを通ったが、まるでこの張り紙のような空気を発する店だった。
手書きではなく、パソコン文字をアナログな方法で中途半端に修正するやり方もとりあえずという感じで、何事にもこんな姿勢でやるようになってしまった。
人間の神経にも寿命というものがあるのだと寂しく思う。
2023/04/15
「冨士クリーニンク」と書いてあるが、もともとは「冨士クリーニング」だった。
濁点が薄く残っている。
それにしても文字が右に寄りすぎな気がする。
「冨」という漢字の白いスキマ部分が点描だ。
「二」は上の横棒がずり落ちて・・・いや全体が水平・垂直から逃げている。
重力からの逃走。
背景のひび割れ、右下のガムテープに対応してちょっと進入している自転車カゴもいい感じだ。
2023/04/11
オークションで買った。
まだ手元にない。
KOKUYO マップケース 5段×2台 。
競り合ったけれど、22000円で落札した。
年齢を考えたら、もう新品もないかなと思うし。
新品で買ったら16万円以上するから、お買い得やったと思う。
今度の日曜に引き取りに琵琶湖畔まで行く。
来年からに備えた小さな倉庫。
2023/04/04

「燃えるゴミ」という表記に慣れていたので「燃やすゴミ」という言い方が新鮮だ。
「燃えるゴミ」は、ゴミを捨てる人の立場で書かれているのに対し、「燃やすゴミ」は、ゴミ処理をする人の目で書かれているように思える。
しかし、もしもゴミを捨てる人の立場で見るなら、「燃やす」ことに積極的な意志を感じる。
完全に燃やし切りたいという願望を起こさせるゴミ箱なのだ。
2023/04/01














